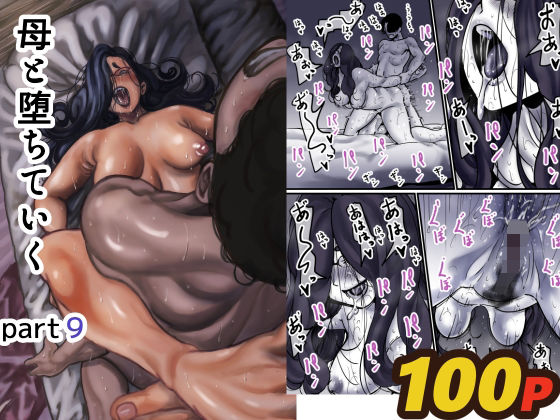去年の正月に伊豆のKという温泉地に妻と旅行に行ってきました。
渋滞を避けて夜明け前に出発したのですが、思ったより道は空いていて、ずいぶん早く旅館に着いてしまいました。チェックインにはまだまだの時間でしたが、長時間の運転で疲れていたので念のためにフロントに聞いてみると「OK」とのこと。喜んだ私たちは、さっそく温泉に入ることにしました。
ここの旅館には大小さまざまな露天風呂があり、地下には混浴風呂もあるとガイドブックに書かれていました。
私としては、妻と2人で広い露天風呂にゆっくりと浸かってみたかったのですが、妻は混浴はどうしてもイヤだと言います。
まあ、私としても他の男には妻の裸を見られたくはないし、ひとり淋しく混浴風呂に入りに行きました。
そこは複雑な形をした洞窟のようになっていて、いちばん奥にある窓(穴?)から外の露天風呂に出られます。
しばらくぼんやりと浸かっていましたが、いつまで待っても他の客の来る気配はありませんでした。
「そういえば、まだぜんぜん早い時間だったんだ・・・」
いそいで浴衣に着替えた私は妻のもとへ走りました。
「混浴」にこだわって、まだ難色を示す妻をなんとか説得してやっと2人で入ることにしました。女性用の更衣室は男性用とは別のところにあり、先に温泉に飛び込んだ私は、妻の来るのを心待ちにしていました。
裸になった妻は、前にタオルをあて恥ずかしそうにやってきましたが、洞窟状の風呂を見たとたんに
「わあ、おもしろいねー、ここ」
と、子供のようにはしゃいでしまいました。
それからは、2人っきりなのをいいことに泳いだり潜ったり飛び込んだりと大暴れのし放題でした。
洞窟の外にある露天風呂も、初めは周りを気にして入らなかったのに、場になじんだとみえて中で少しのぼせると涼みに出たりしていました。
だいぶ時間がたったでしょうか、そろそろ他のお客がやってきているのが遠くにある駐車場に車が集まってきているのでわかりました。
「そろそろ出ようか?」
「もう少し入ってようよ。私、こんなにのんびり温泉に浸かるの初めてなの」
「でも、そろそろ他の客も来始めてるよ」
「少しぐらい見られても平気だよ。中は結構暗いからぼんやりとしか見えないわ」
最初とはうってかわった妻の態度には少々驚きましたが、普段は専業主婦で家にこもりがちなのでストレス発散の意味もあるしと、もう少し入っていることにしました。
ほどなくして洞窟風呂の入り口でガヤガヤと男の声がしました。
「来たな」と、なぜか男である私が身を固くしてしまいました。
妻にも男たちの声が聞こえているはずですが、何事も無いような顔をしてスイスイと泳いでいます。
そして洞窟の扉が開かれました。
私は何故か胸が高鳴ってしまい、妻の手前、平然を装うために勢いよく顔を洗いました。
妻の裸を見られるくらいでうろたえるような男とは思われたくなかったからです。
間もなく、湯煙の中に数人の男の影が現れました。
入って来た男たちの第一声は
「なんじゃこりゃあ?真っ暗で何にも見えねえぞ」でした。
長いこと入っている私たちはすっかり目が慣れてしまっていたのですが、外から来た人にはずいぶん暗く感じたことでしょう。
それに夕方も近くなり、外もだいぶ日が陰ってきていました。
「電気ないの?電気?」
「うわ、真っ暗だよ」
「おっ、ここにスイッチがあるぞ」
パチッ。眩い光に、一瞬目をしょぼつかせてしましました。
「あれ?先客がいたんだ。こんにちはー」
「こんにちは」
挨拶を返しながら相手を見てみると、私より10歳は年上と思われる中年の3人組でした。
なにやら陽気そうな人達で、私は内心ほっとしました。
振り返って妻を見ると、首まで湯に浸かったまま私のすぐ後ろに隠れるようにしていました。
「アレ?そっちは女のひと?いいねえ〜夫婦で仲良く混浴だあ〜」
3人は既に結構酔っているようで、仲間内で他愛もないバカ話をしていました。そのうちに私たちにも話題を向けてきて、妻も交えての世間話が始まりました。
私はどちらかというと人見知りするほうなので、初対面の人とはなかなか打ち解けられないほうなのですが、妻は物怖じしない性格で、人なつこく、誰とでもすぐに仲良くなってしまうので、こういう場では助かります。
はじめは私も相づちを打っていましたが、そのうちに聞き役に回るようになってしまいました。
しばらくすると、だんだんのぼせてきたのか、妻が湯船に腰掛けました。男たちは話しを続けながらも、妻の身体をさりげなく観察しているようです。
もちろん妻はハンドタオルを胸から前に垂らしているので肝心な部分は見えませんが、濡れたタオルはピッタリと張りついて、身体のラインがはっきりとわかりました。
自分の妻ながら、なぜか私はドキリとしてしまいました。
男たちと妻は話しが合うようで、話題は次から次へと代わります。
そのうちに妻は、話しに夢中になっているのか、男たちへの警戒心を解いたのか、胸を隠している手が微妙にずれてきていました。ときどき身振りを加えたりするとタオルを抑えているのがおろそかになり、乳首が見えそうになります。
男たちもそれを気にしているようで、視線は胸のあたりをさまよっているようでした。
「猿腕って知ってる?」
「えっ?なんですかそれ?」
「こうね、手のひらを合わせて腕を伸ばしたときにね。肘と肘がくっつくのをサルウデって言うんだよ。やってみな、普通はつかないんだけどね」
「えっ?こうですか?」
妻は言われた通りの動作をしました。そう、タオルから手を離してしまったのです。
「えー?つかないですよ」
男たちの意図にまったく気付いていない妻は、単純に不思議がっています。
濡れたタオルは幸いにも両腕にはさまれてかろうじて胸を覆っていました。
「こうするんだよ」
いちばん小柄で毛深い男が同じ動作をすると、肘から先がぴったりとつきました。
「ああ、本当だー、おもしろいですね」
「こういうのは生まれつきの骨格の違いだね。」
「このおじさんは猿みたいな顔をしてるけど、本当に猿なんだよ」
私は、ただぼんやりと話しを聞いているのにも疲れてきて、温泉から上がってみんなから少し離れた洞窟の窪みに行って横になりました。
そこは、電球の灯かりの届かない暗い場所でしたが、こちらからは妻の様子はよく見えます。
そういえば、こうして妻の裸を見たのはいつ以来だったでしょうか。
普段の暮らしの中では妻の裸をじっくりと見る機会などほとんどありませんでした。
一緒に風呂に入るということもないし、夜の営みのときでも灯かりは消しています。
私たちは、結婚して4年、知り合ってからは10年になりますが、初めてのときに妻がひどく恥ずかしがって、それ以来なんとなく妻の裸を見るのは妻に悪いような気がして
あえて見ないようにしてきたのかもしれません。
もちろん夫婦生活では互いに口腔愛撫などもしますし、そのへんのことはノーマルだと思っていますが、なぜか「裸を見る」ということだけが今までなかったのでした。
だから、いま目の前で、知り合ったばかりの中年男たちと談笑している裸の妻というのは、自分の妻でありながらも、なぜか未知の女性のような錯覚を感じてしまい、とても不思議な気がしました。
裸電球のやわらかな光に照らされて、うっすらと汗のにじんだ妻の身体が湯煙りの向こうに輝いて見えました。
自分の妻がこんなに美しい肢体をしていたなんて…恥ずかしながら、今ごろになって気付いたのでした。
私は横になって、ひんやりとした岩肌に火照った身体を大の字に伸ばしたまま、ついウトウトと眠ってしまいました。
目をさますと、面前に妻の顔がありました。笑っています。
「目が覚めた?ずいぶん疲れてたみたいね。ヨダレたらしてたよ」
「えっ?」
あわてて濡れた口元を拭いました。照れ隠しに温泉をすくい、おおげさに顔を洗いました。
「おじさんたちはもう上がったの?」
「ちょっと前に出たよ。私たちもそろそろ部屋に行こうよ」
「ああ、もう外は真っ暗だ。結局ほかには誰も来なかったんだね」
「そうだね。誰も来てないよ」
「ずいぶん楽しそうにしてたみたいだけど、面白そうな人たちで良かったね」
「う〜ん。でも、いい人そうに見えてもやっぱり男は嫌らしいよ」
「えっ??何か変なことされたの?」
「変なことっていうか……」
「何があったの?怒らないから言ってごらん」
「あなたがこっちに来てまもなくイビキをかいて寝ちゃったのよ。それで、あなたが寝たっていうのがあの人たちにもわかったのね」
「それで?」
「それで、話しの続きで、あの猿みたいなおじさんがすごく身体が柔らかいの。脚なんて180度に開いて、前にペタっと胸がつくのね」
「ほう、50歳くらいに見えたけどすごいね。何かやってるのかな」
「なんだか、マッコーホーとかいうのをやってて、それを続けると80歳のおじいさんでもそんなことができるらしいのね」
「へえ、すごいね」
「で、それをわたしにもやってみろって言うの。健康にいいからとか言って」
「ここで?」
「そう。信じられないでしょう?私、この格好だよ」
「じゃあ、断ったんだろ?」
「あたりまえでしょう。おじさんならチンチン丸出しでやってもいいかもしれないけど、私は無理ですって断ったわ」
「おじさんのチンチン見たの?」
「見たんじゃなくて見えたの!目をそらすのも不自然な感じがして…」
「君に見せたかったんじゃないの?大きかった?」
「嫌ね。でも、普通なんじゃないの。よく知らないけど…」
「それで、どうなったの?」
「それで、いちおう断ったんだけど、おじさんたちもしつこくて、それに、その場の雰囲気でなんとなく断りきれなくて…」
「じゃあ、結局やったんだ?」
「うん…。ごめんね」
「べつに謝らなくてもいいよ。怒っちゃいないよ。それで、具体的にはどんな格好をしたの?ちょっとやって見せて」
「えーっ?ここで?恥ずかしいよー」
「だって、おじさんたちの前では出来たんだろ?じゃあ、僕の前でも出来るはずだよ」
「もうー。いじわるなんだから」
「さ、やってみてよ」
「う…ん。まず、こう座ってから…」
私は、表面上は平静を装っていましたが、内心では激しいショックを受けていました。
いままで誰にも、というか私にすら裸を見せなかった妻が、今日知り合ったばかりの中年男の前で、大胆にも開脚運動までしてしまったのです。
自慢ではありませんが…いや…本当は自慢になりますが、妻は私のひいき目を抜きにしても、かなり美しい女性だと思います。
中学・高校と水泳で鍛えた身体は、運動をやめて10年を経てもそのスタイルを維持していますし、ルックスの良さで、当時ある雑誌に「水泳界のアイドル発見」として見開きで紹介されたこともありました。
ただ、小柄(154センチ)なのと、選手としては細身であまり筋肉が付きづらい体質のために記録としては平凡なものしか残せませんでしたが、一時は「追っかけ」と呼ばれる巨大なカメラを持ったファンが何人もいたほどでした。
そして大学に入ってから私と知り合い現在に至るわけですが、妻は私にとってもアイドルであり、また大切な宝物でした。
実は、私は自分でも少し異常かな?と思うくらいに嫉妬深い男なのです。
ただ、私自身がそういう嫉妬深い自分を「男らしくない」と蔑む気持ちも持っているために、かなり努力して妻には悟られないようにしてきました。
また、前に妻が、やきもち焼きの彼氏に悩む友達の相談にのっていたときに「そんなに自分の彼女が信用できないなんて…」と言っていたことも心に残っていましたので「寛大な男」という自己演出を続けてきました。
しかし本心としては「独占欲の固まり」で、とにかく妻には私ひとりしか見て欲しくないし、妻が他の男から性欲の対象として見られるのがたまりません。だから妻には私の好みだからと言って、普段からなるべく地味なメイクで地味なパンツルックなどをしてもらったりしています。夏でも露出の多い服装はダメ、海水浴でさえ水着の上にTシャツを着せるありさまでした。
我ながらそんな自分をちょっとおかしいのでは?と思うこともありますが、やはり妻は自分だけのものであって欲しいという気持ちは強く、これも自分にはもったいないほどの妻ゆえのことと、いつも自問自答している次第です。
さて、妻の再現が始まりました。まず、平らな岩の上にタオルを敷いてその上に脚を揃えて伸ばし座ります。この時点ですでに胸は隠してはいません。
「おじさんたち、胸が大きいとか言ってた?」
「形がいいって。でも、乳首が小さいって笑ってた。旦那にあんまり吸われてないなって」
カッと頭に血が上るのがよく分かりました。妻の、この胸を見られてしまったのか…。
「ははは…。たしかにあまり吸わないけどね。それで、この後は?」
「いったん揃えてから左右に開いて…」
妻が両足を大きく広げました。濡れた淡いヘアーが丸見えになりました。贅肉のない白い下腹がかすかに波うっているのと、脚の付け根の筋が張りつめているのが妙にエロチックでした。
「けっこう柔らかいんだなあ。180度くらいすぐに開くんじゃない?」
「昔、ずいぶんストレッチやったからね。でもこの格好は裸じゃかなり恥ずかしいものがあるね。」
「ああ、でも肝心なところは見えてないから大丈夫だよ」
たしかに、こんなに脚を開いているにもかかわらず性器そのものは見えていませんでした。不幸中の幸いというか、少しだけホッとしたのですが…。
「こう開いた状態から身体を前に倒していくの」
妻が身体を前に倒していきます。
「頭じゃなくて、お腹を床につけるようにするんだって…」
妻もそうとう身体が柔らかい方でしょう。もう少しでお腹が床につきそうです。
「少し背中を押してみて。さっきはちゃんとついたから」
私は言われたとおりに背中を押そうと妻の背後に回り、そして愕然としました。
正面からはヘアーしか見えなかった妻の秘部でしたが、後ろからは丸見えでした。
蕾んでいるはずの肛門はやや開きぎみになっているし、普段は閉じているはずの性器もすっかり広がってしまい、ピンク色の中身まで見えていました。
「背中っていうより、腰のあたりを押してね」
「おじさんにも押してもらったの?」
「うん。交代で3人で押してくれたよ」
見られたのか……。妻のすべてをあの中年男たちに……。
激しい嫉妬の念がわきました。しかし、なぜか私の下半身は激しく屹立していました。
「ねえ?この格好って、やっぱり見えてるの?」
「えっ?ああ、見えてるね」
「おじさんたちが、若いから色がどうだとか形がこうだとか小声で言ってたのが聞こえたの。最初は胸のことだと思ってたんだけどねぇ…」
「触られたりしなかった?」
「しなかった。背中を押してもらっただけ。でも恥ずかしいなあ、見られてたのか」
私は片手で腰の少し上を押しながら、もう一度お尻を覗き込みました。
真っ白なお尻の間に見える、ややくすんだ色の風景は妙に生々しくて、いかにも生殖器という臓器そのものでした。
そして、開いた性器からは、なぜか透明な粘液が一筋の糸を引いていました。
妻は…感じていたのか…? あの男たちに見られて…?
後悔・嫉妬・興奮……さまざまな思いが私の中でせめぎ合っていました。